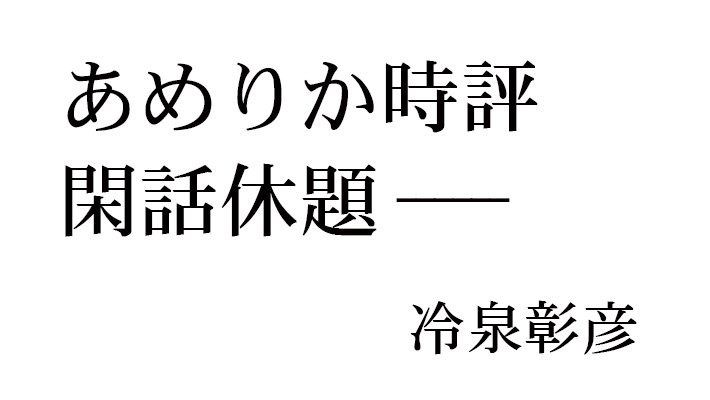3年間我慢していたが、8月末から9月初めにかけて野球見物を再開、短期間にヤンキースとメッツの主催ゲームを観戦する機会を得た。まずヤンキースタジアムに足を踏み入れた時は、豪雨の影響で着いた時には3回表までゲームが進んでいたこともあり、超満員のスタジアムに驚かされた。コロナ禍が始まって以来、4万人を超える人が一同に会しているわけで、慣れるのには多少時間がかかったのは事実だ。
更に10日後にメッツの本拠地、シティ・フィールドにも行ったのだが、その経験を重ねる中で感じたのは「希望」である。試合が面白かったのは勿論だが、スタジアムでの経験は素晴らしいものだった。現在のニューヨークはコロナ禍による深い痛手の中にあり、人口流出、治安悪化、衛生状態の悪化、最高裁による銃規制の妨害など問題が山積している。けれども、ニューヨークはこの難局を乗り越えるに違いない、そう感じさせるものがあった。
まず驚いたのは、野球に対する姿勢だ。ヤンキースタジアムでは、ヤンキースが攻撃中に凡フライが上がっても誰も何も言わない。シーンとしているのである。別に観客が醒めているのではない。一方で、ホームラン性の当たりが飛び出すと、打った瞬間に「ウォーッ」となるからだ。つまり、打った瞬間に凡フライかどうかをほとんど全員が「分かる」のだ。野球をよく知っていて、しかもTVでなく生の野球を経験している人が圧倒的ということであり、これは昔とは違う。ファンの年齢層は若くなっているが、しっかり野球好きが育っている。この傾向は、メッツのシティ・フィールドでも感じた。
全く誰もマスクをしていないという事実には、最初は戸惑った。だが、よく見てみると感染対策を気にしていないとか、否定しているわけではない。通路を行き交う際、奥の席に行くために手前の席の人たちに一旦立ってもらう際など、人々は実に礼儀正しい。3フィートの「ディスタンス」は無理でも、最後の「5インチ」は気にするという風情だ。席を立って通路を空けながら、みんな微笑んでいる。この丁寧さ、気遣いというのはコロナ禍の前とは全く違う。苦境を経験した上で、お互いが気持ちよく過ごすための知恵を共有しているのだ。
野球そのものも進化している。投手が100マイル(160キロ)の速球を投げるのは、もはや当たり前で、98マイルのシンカーという沈む球まで駆使する投手も多いが、上手いバッターはそれにも対応している。TV中継で見て知っていても、実際にこの目でそのようなハイレベルの「対決」を見ると隔世の感がある。
球場における観客の動線もよく考えられている。旧ヤンキースタジアムやシェイ・スタジアムの時は、試合終了後に球場から出るのに何十分もかかったが、ヤンキースもメッツも新しい球場になって改善していた。今回は、以前にも増してスムーズであり、コロナ禍への対策として要員の配置などマネジメントが向上しているのを感じた。
観戦を盛り上げる映像や音響も昔とは違う。特にシティ・フィールドの場合は、女性や子供を意識した斬新な応援の仕掛けに感心した。人気のリリーフ投手、エドウイン・ディアスが登場する時は、トランペットの音楽「ナルコ」が鳴り響いて大変な盛り上がりになるとか、新しい工夫がどんどん取り入れられている。
とにかく、以前と比較して運営側も様々な見えない知恵を使っていること、何よりもマスクなしで自由に楽しんでいるように見えて、人々は必要な気遣いはしていること、その全体が作り出す前向きの雰囲気、「希望を感じた」というのは、そういう意味だ。ヤンキースもメッツも優勝を争っているという成績面での明るさもあるが、それ以上のものを感じた。
NY全市の治安問題、リモートと出勤のバランスを取って街の活気を回復する問題など、全市にはまだまだ難問が山積している。けれども、野球などのカルチャーが、コミュニティの求心力として健在というのは大きい。この秋は、METオペラ、本拠地が改装したNYフィルなどもノーマルモードで本格的に活動する。こうしたカルチャーの力をベースに、経済の再生を行うだけの底力はこの街には十分にあるはずだ。
(れいぜい・あきひこ/作家・プリンストン在住)