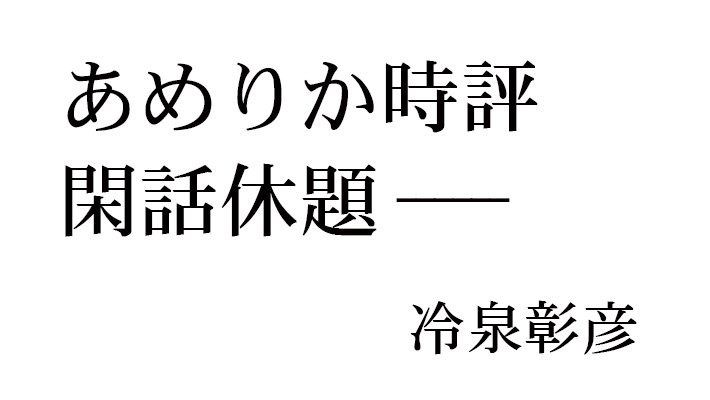東京都議選を巡る騒動をアメリカから見ていると、何とも異様としか言いようがない。結果として自公連合は過半数を取れず、反対に惨敗が予想された都民ファーストの会が善戦した。同党は、事実上は小池都知事の率いる地域政党だが、知事自身は過労のため入院して選挙には距離を置いていた。その小池氏は選挙戦終盤で突如復帰し、投票前日には酸素ボンベを傍らに選挙運動を行う姿が報じられたことで同情票が入ったとされている。
一連の行動を通じて小池氏は、選挙における政策論争には距離を置き、自公政権への批判は避けつつも自らの政治的影響力の誇示には成功したようだ。そのため、今秋に予定されている総選挙においては、知事を辞職して自民党から衆院選に出馬し、次期総理総裁を狙う可能性が取り沙汰されている。反対に、自民党の菅政権に関しては、五輪とコロナに関する世論との対話に失敗した結果の敗北という評価がある。
話としては面白いが、都議選の総評としては、やはり異様である。政策決定としては何も決まらなかったからだ。オリ・パラ開催に関する民意は曖昧であったし、コロナ対策への審判があったわけでもない。まして、急速に悪化した都財政への対策も、急増する東京の高齢単身世帯への対処も、荒川氾濫に備えた防災体制など東京都の喫緊の課題についての判断もされなかった。
考えてみれば、ここ数十年の国政選挙において政策選択として意味があったのは、2012年の第二次安倍政権登場における金融緩和政策への支持ぐらいだが、これも民主党政権への批判票が押し上げただけだ。アメリカ流の見方からすれば極めてリベラルな金融政策「アベノミクス」について、意味合いが正確に理解された上での支持ではなかった。その安倍政権は、その後は保守票を政治的求心力にしながら中道政策を続けるという綱渡りを続けたが、具体的な政策について民意を問うことはなかった。そして、現在は菅政権に対しては漠然とした不信感が広がる一方で、政策提案を持たない小池氏の政治的存在感が増している。
こんなことでは、経済再建のための改革が民意の後押しで強力に実施されるなどということは起こり得ないだろうし、そもそも東アジアの中で民主主義のお手本として胸を張ることも難しい。
解説ならいくらでもできる。主権者が絶望と不信のあまり代表への委任をしない現象だとか、そもそも日本社会は膨大なノンポリ人口でできているとか、全てを「永田町風雲録」的なドラマにして説明してしまうメディアの罪であるとか、どれも全くの間違いではない。
けれども、異様な政治風土の背景には構造的な3つの問題が横たわっている。
1つは、世論形成に大きな影響力を持つ賃金労働者の多くは、終身雇用契約により企業や団体に帰属しているという点だ。彼ら彼女らに取っては、生活設計を左右するのは年功序列集団内における地位の安定であり、景気動向や政策の影響は限定的だ。投票行動が明確な利害ではなく、印象論に左右されがちなのはこのためだ。
2つ目は、異なる利害を代表する政党が少ないという問題だ。例えば、生活に困窮している非正規労働者を代表する団体はない。子育てや現業の現役世代の代表も少ない。その一方で、自営業や高齢世代、また地方の補助金の絡んだ産業に関しては、利害代表がある。つまり、自分たちの代表を持っている層と、持っていない層が偏在している。
3点目としては、納税者意識の問題だ。国民がほぼ100%「タックス・リターン」の手続きをするアメリカとは違って、日本では年税額の計算を企業が代行する年末調整制度が残っている。地方税に至っては、1年遅れで企業が月払いで徴収して終わりである。従って、増減税への関心は少なく、財政規律の論議が印象論になりやすい。財政と税負担が厳しい利害計算を突きつけるはずの地方議会選挙が、低投票率下のイメージ選挙となるのはこのためだ。
日本の民主政治が異様なのは、日本人の民度が低いからではない。問題の多くは制度に原因があり、そこにメスを入れる必要がある。
(れいぜい・あきひこ/作家・プリンストン在住)