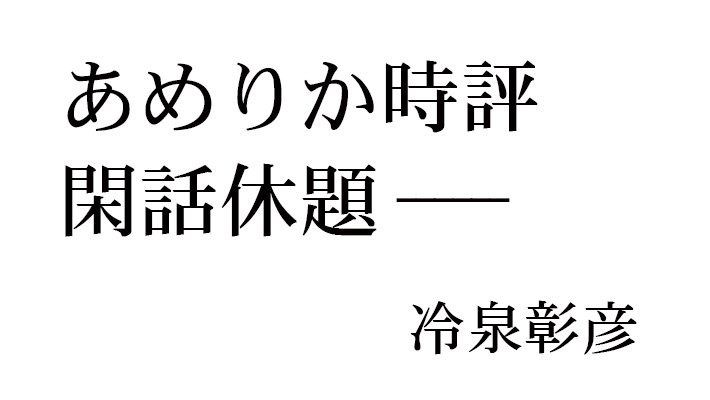あめりか時評閑話休題 冷泉彰彦
日本における新型コロナウイルス対策を、アメリカから見るのは何とも歯痒く、辛い。陽性者比率、死亡率を比較するのであれば、日本の数字は極めて優秀だ。人口比で見てみれば20分の1以下であり、この傾向は最新のデータでも変わらない。にも関わらず、大阪などでは医療崩壊で救命のできないケースも発生したし、何よりもワクチンの接種は遅れた。結果的に、GDPへのマイナス効果はアメリカよりも厳しい。こうした推移について厚労行政の責任とするのは簡単だ。だが、長く複雑な歴史的経緯を考えるのであれば、必ずしも当局を責めて済む話ではない。
まずワクチン接種の遅れだが、根本にあるのは日本社会に根強いワクチン忌避感情だ。1970年前後までの日本では、感染症の予防接種は厳格に義務化されていた。だが、70年代以降、状況が変わった。副反応を経験した患者やその家族が「同じような苦しみを受ける人を根絶したい」という感情を抱くと、メディアや弁護士が群がって支援してワクチンの「義務化」をどんどん潰して行ったのである。この「反ワクチン」の流れに加えて、一連の薬害問題が事態を悪化させた。薬害エイズ事件に際しては、当時の厚生大臣が政治パフォーマンスに走る中で、厚生官僚の逮捕という事態まで起きた。
これでは、「mRNAという遺伝子技術を使った新世代ワクチン」などという新技術を、率先して認可する勇気を出せというのは無理な話である。そんな中では、世界各国で大規模な接種実績が進み、その効果が明らかとなるのを待つしかなかったという推測が成り立つ。社会に満ち満ちている不信感に対抗するには、それが唯一のシナリオだからだ。
日本におけるワクチン接種に関して、歯科医への拡大は進んだが、アメリカのように薬剤師による接種は実現していない。一般的には、医師会が既得権を握って放さないからという解説がされている。けれども、実情としては、薬剤師による接種で事故が起きた場合に監督の医師が厳しく批判され、場合によっては逮捕という可能性もある中では、医師会も防衛的にならざるを得ないのではないか。
コロナ病床の増床が進まない問題も同様だ。4月から5月の大阪府の場合など、感染拡大の勢いに合わせてコロナ病床を増やせば、その分だけコロナ外の診療には支障が出たであろう。その場合にコロナ外で救命できる患者を救えなかったら、医療過誤事例として最悪の場合は医師に逮捕状が執行される可能性もあるのが現行の制度である。そう考えると、問題には裁判所や警察も含めた複雑な構造があるわけで、厚労省や医師会が保守的だという説明だけで済ますことはできない。
融通の利かない制度の背景には、社会に統一された常識(コモンセンス)がないので、ルールを決めたら杓子定規に適用するしかないという問題もあるだろう。更に突き詰めて考えると、問題の原点には江戸時代から綿々と続く「お上と庶民」の相互不信という問題に行き着く。医療を縛る硬直した規制の多くは、こうした不信の産物だからだ。
今回の五輪開催の是非をめぐっては、この相互不信が思い切り噴出した感がある。「庶民」の側は、ワクチンの効果など無視して外国人の大量入国に勝手に怯えながら、五輪反対のムードをエスカレートさせている。反対に「お上」の側は実施へ向けて引くに引けなくなってきた。政府としては、さまざまな矛盾点については大会が成功すれば「結果オーライ」となるという読みから開催という賭けに打って出ている。説明を渋っているのは、賭けの危険性を薄々感じているからであろう。更に、7月の東京都議会選挙と、10月と言われる衆議院選挙という政治日程が、政権与党を「五輪強行開催」という危険なギャンブルへと追い詰めている。
この相互不信があるレベルを超えてしまうと、大会の成功も難しくなる。国民の8割が反対という状態が続くようでは、各国選手団に「感染拡大で危険な国」という印象を与え、大会の足を引っ張りかねない。そうしたシナリオを回避できるか、いよいよ正念場に差し掛かってきた。
(れいぜい・あきひこ/作家・プリンストン在住)