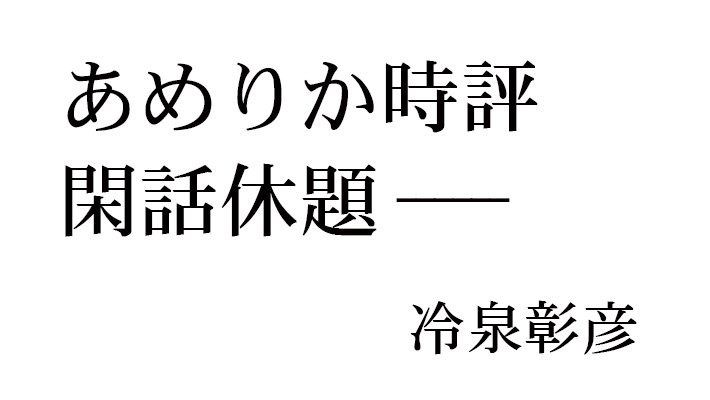新しい年が明けた。終わらないコロナ禍に加えて、ロシアの軍国化、中国の統制強化、西側各国でのポピュリズム禍など、日本を囲む環境は依然として厳しい。経済にも世相にも暗い影が濃くなるのを感じる。加えて日本では、雇用システムも、教育も、IT活用も、また日本語と紙による非効率な事務作業にしても、改革が実行できずにズルズルと生産性を下げており、競争力もジリ貧だ。そんな中で、変化するだけのエネルギーも失いつつあるようにも見える。
社会の変革というのは難しいが、人の生き方を変えることはできる。そんな中で、日本社会における閉塞感を解きほぐす対策として、年のはじめにあたって、日本語の再生を考えてみたい。
日本語の再生というと、美しい日本語を取り戻すべきだとか、反対に若者の気軽な表現を認めようなどというイメージが浮かぶかもしれないが、そうではない。問題は日本語における広い意味での敬語にあると考えられる。現代の日本語文法では、敬語など日本語の待遇表現には3種類があるとされる。目下が目上を敬う「尊敬語」、つまり「先生がおっしゃった」という種類、自分を低めて相手への敬意を示す「伺う、申し上げる」などの「謙譲語」、そして話し相手に敬意を示す「です、ます」表現などの「丁寧語」である。
私は、このような日本の「敬語」の全体は「乱れに乱れている」と考えている。最大の問題は謙譲語で、とにかく新しく店員になる人や、就職する人には「上司と取引先(消費者)は制御不能な暴君」だという大前提から、その暴虐から自身と組織を守るためにミサイル迎撃システムのような防衛表現が推奨される。その結果が「〜させていただく」の連打ということになる。ゲーム感覚で対応できればいいが、相手の攻撃を交わすことで、自分のメンタルを守るのはゲームとしてもかなり難度の高い部類になる。
また、若い世代には敬語を駆使して自分を守ることへの疲労と嫌悪から、敬語抜きの表現、つまり「だ、である」調のことをタメ口と呼んで過大評価する傾向もある。実は「だ、である」調というのは「よ」とか「ね」などの強調や感情を表す助詞と容易に結びついて「同調圧力」を湧き起こす厄介な存在だし、その結果として内輪言葉の「内閉化」とか「新入メンバーの排除」などの暴力性も生んでしまう危険すらある。けれども、若者にはそうした自覚はなく、嘘くさい尊敬語や、卑屈な専守防衛である謙譲語に疲弊したメンタルを解放するのは「タメ口」だと思っているから始末が悪い。
著書の『関係の空気 場の空気』(講談社新書)で詳しく述べているが、私はこうした状況を救うのは「です、ます」表現であると考えている。一般的には「丁寧語」と言われているものだが、「だ、である」が文語(書き言葉)のデフォルトなら、この「です、ます」は話し言葉のデフォルトだと言っても良い。話者が話し相手の人格を認めて大切にする、また余計な感情や権力行使を避けつつ、相手との適度な距離感を保つことができる、これが「です、ます」の最大のメリットである。若い人は、冷たいとか事務的と言って嫌うが、実はメンタルへの負荷も少ないのがこの「です、ます」ではないだろうか。
新しい年にあたって、一つだけ提案をしてみたい。それは、俗に言う目上の立場から、目下の立場に対して「です、ます」を使用するということだ。客から店員へ、上司から部下へ、教師から生徒へ、親から子へ、先輩から後輩へ、従来であれば「タメ口」に「ね」とか「よ」といった助詞を絡ませて権力行使を行い、対等性を壊していた関係が、「上から下へのです、ます」を徹底することで、自然な距離感とともに健全な対等性を持ってくるはずだ。その上で、例えばビジネスの現場で「下から上への積極的な情報提供、問題提起」がされるようになれば、低迷する日本の生産性も向上するに違いない。
具体的な例としては、昨年12月のサッカーW杯では日本のTV中継を解説した本田圭佑氏が、自分の下の世代の現役選手を「さん付け」で呼び、その品格が話題になった。この発想法は大いに参考になる。また、同じく昨年暮れに13代目を襲名した歌舞伎の市川團十郎丈は、記者会見などの席で、息子さんの8代目新之助に対して「あなた」という二人称を使い「です、ます」を混ぜた表現で応対していた。役者人生へと向かう9歳の少年を一人の人格として認める姿勢は、芸道に人生をかける者ならではの重みを感じると同時に、新時代の親子関係を示唆しているとも言える。
新しい年、「だ、である」を使った同調圧力、権力行使を一旦止めてみて、「上から下」への「です、ます」を試してみてはいかがだろうか。まず、人間関係が健全化され、チームのモチベーションが向上し、個々人のメンタルにもいい影響が出るはずだ。そんな一人一人の改革が積み上がることで、社会に明るさが出てくる、そんな年になればという思いを込めつつ新年を迎えたい。(ジャーナリスト、プリンストン在住)